アイリッシュ・ツイード
Irish Tweed
アイルランド産ツイードの総称。ドニゴール・ツイードなどがこの中に含まれます。
インディアン・マドラス
Indian Madras
本来はインド・マドラス地方で手織りされる綿布のことで、カラフルで複雑なチェック柄が特徴。本物は民芸品に近いので、チェックの大きさが不揃いであったり、染色堅牢度に問題があったりすることが多いようです。
オックスフォード・グレイ
Oxford Grey
濃い霜降のグレイのこと。
カルゼ
英国サフォーク州のKERSEYの地名をつけたもの。経に杢糸を使った、畝のはっきりした急斜紋の厚手の綾織物。非常に丈夫なので、耐久力の必要な軍服やコートなどに使われています。カバート・クロスというのが正式な呼び名。
サキソニー
Saxony
はじめドイツ南部のサキソニー地方産のメリノ種羊毛を使っていたことから、この名があります。綾織で表面に幾分毛羽を残した、手触りの柔らかい織物の総称として使われています。
シェットランド・ツイード
Shetland Tweed
スコットランド北端にシェットランド島という小さな島があります。ピートと苔に覆われた絶海の孤島で、ここに棲む羊は、岩磯で海藻を食べて生育するため、極めてソフトでスポンジーな羊毛が採れます。この毛を使って織られたツイードが「シェットランド・ツイード」ですが、このハンドリングを似せて作ったイミテーションが多いようです。
スコッチ・ツイード
Scotch Tweed
スコットランド産ツイードの総称。チェビオット、シェットランド、ハリスなどのツイードはこのスコッチ・ツイードの中の1品種です。
チェビット
Cheviot
スコットランドとイングランドにまたがるチェビオット丘陵原産の山岳種羊の一種。英国種羊毛の中では、強力、光沢ともにすぐれていて、紡毛、梳毛両方に使われています。この羊毛を使った紡毛織物をチェビオット・ツイードといいます。
ツイード
Tweed
スコットランドやアイルランドを主産地とする、、伸縮性に富んだザックリした手触りの紡毛織物の総称。語源は、スコットランドのツイード河周辺の産地から送られてきた綾織物(TWILL)の送り状を、スコットランドの語形TWEELと、川の名前Tweedとを読み違えたことに端を発するという説が有力です。
ディストリクト・チェック
District Check
ディストリクトの和訳は「地方」です。クラン(士族)・タータンを使えない階級がデザインしたチェックで、「準タータン」とも呼ばれています。クラン・タータンよりも地味な配色が多く、それぞれに名前がつけられています。
ドニゴール・ツイード
Donegal Tweed
アイルランド北部のドニゴール地方の農家が、副業的に手紡し手織りした平織のツイードのこと。色ネップが入っているのが特徴で、日本では「ホーム・スパン」と呼ばれています。

バナックバーン・ツイード
Bannockburn Tweed
霜降の杢糸と黒糸とを使ってシャークスキン目風に織ったツイードで、チェビオット羊毛を使ったものが多いようです。梳毛糸と紡毛糸を使い併せた薄手でシッカリしたツイードなので、スーツ地としても使われます。スコットランド中部の地名から由来しています。
ラム・ウール
Lamb’s wool
生後約半年の仔羊をラムといいます。その毛は極めてソフトですが、毛足は短く、産毛量が少ないために希少価値が高い原毛です。
パーム・ビーチ
Palm Beach
アメリカ・フロリダの高級リゾート地を商品名とした夏服地。経糸に綿糸または綿糸と毛糸の交撚糸を使い、緯糸に粗い原料の毛糸を打ち込んだ、サラッとした肌触りの夏服地。
ハリス・ツイード
Donegal Tweed
スコットランド北西のハリス島に棲息する羊の毛を紡毛し、自然色のまま、または植物性染料で手染めした糸で毛織りしたもので、半幅のものが本物。手触りは極めて厚く、ケンピーと呼ばれる染まらない白い「死に毛」が混じっているのが特徴。正真正銘のハリス・ツイードには、協会の転写マークが捺されている。
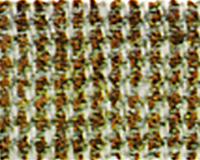
ベネシャン
Venetian
イタリアのベニスの地名にちなんで命名されたといわれています。経糸の密度を多くして急斜紋とし、地合いを密にして柔らかく仕上げた織物。
ボタニ・サージ
Botany Serge
生後約半年の仔羊をラムといいます。その毛は極めてソフトですが、毛足は短く、産毛量が少ないために希少価値が高い原毛です。
ロンドン・シュランク
London Shrunk
仕上がった織物を、縫製の途中や仕立て上がってから、狂いが起きないように、地詰めする工程をシュランクといいます。ロンドンの専門業者がこの工程を考え出したので、この名があります。本当のロンドン・シュランクは、湿った布の間に、全幅に拡げた毛織物を挟み込み、折り畳んだ状態で、一昼夜寝かしたあと、フリーな状態で吊るして自然乾燥させる、という全くの手作業で行います。